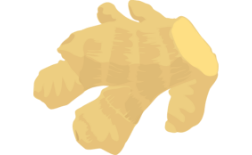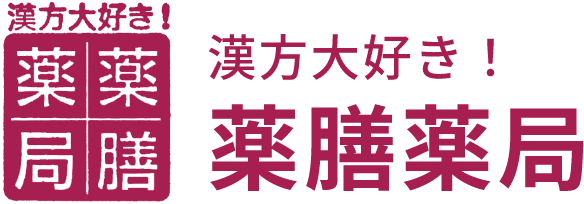薬膳学と分子栄養学のダブルの力
漢方治療を支えるのは何といってもお食事です。
人間は食べなければ生きることはできません。
しかし、食べ物次第で健康にも不健康にもなります。
自分にとっての正しい食事のハウツウを学ぶことは大切です。当店は日本人に合わせた薬膳学と分子栄養学(細胞レベルの代謝学)の二本柱で、病気を治し体質を変える食事のご指導を致します。

日本人に合わせた薬膳学と分子栄養学(細胞レベルの代謝学)の二本柱
例えば、
アトピー性皮膚炎の方は、皮膚の炎症と痒みでお困りですから
細胞レベルで
- ①炎症が起きないための理論
- ②痒みが起きないための理論
理論をまず理解していただき、それから、治療としての薬膳的お食事内容を学びます。
食事は薬
ご自分の病気の原因である細胞レベルでの栄養的知識を持つことは、
治療中の自分の食事の見直しに、絶対に必要なステップです。
理解が出来たら、「食事は薬」という発想で、薬膳のやり方を学びます。
何故海藻をもっと摂らなくてはならないか、何故レタスではなくてはキャベツを食べなくてはならないのか、何故肉ではなく魚を食べるべきなのか等。
沢山の知識を持ち実践なさることで、漢方薬は何倍もの威力を発揮します。